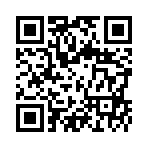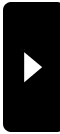2014年12月21日
プレゼンで聞き手にとって価値ある提案をできるか
良いプレゼンテーションとは、
聞き手に「ああ今日このプレゼンを聞いて
本当に良かった、得した」と思ってもらえる
プレゼンである。
聞き手は貴重な人生の時間を割いて
話し手に提供してくれているのだ。
その時間に見合う、あるいはそれ以上に
価値のあるものを提供しなくてはならない。
だからこそプレゼンの準備では
聞き手にとっての価値を徹底的に
深掘りする作業が不可欠なのである。
もちろん聞き手にとっての価値は
人によって様々だから、
不特定多数のような
属性がバラバラの聞き手が対象の場合、
すべての聴衆に満足してもらえる価値などは無い。
しかしプレゼンはスピーチと異なり、
必ず何かの目的があるはずなので、
そこに集まった人たちには共通する
価値があるはずである。
その集まりに「せっかく来てくださった
皆さんに何を提供すべきなのか」
徹底的に調べ、考え抜く。
例えば初心者向けの不動産投資セミナー
があったとしよう。
参加者が最も望んでいることは
起業の話でも株式の話でもないはずだ。
参加者が聞きたいこと、
それは安定的に不動産で収益を
上げることのはずである。
同じように一対一の営業シーンだったら
対面するお客様が最も望むことは
何なのか考える。
就職面接の場面なら、
面接官が採用する人間に求めている
ことは何なのかを突き詰める。
どれもあたり前のことだが、
プレゼンの場面では多くの場合
これが出来ていない。
では聞き手の求めていることが
想定できたら次にすることは何か。
長くなったのでそれは次回に。
2014年12月20日
プレゼンテーションにおける話し方の巧拙
話し方の巧拙は、プレゼンテーションにおいて
どの程度重要性があるのだろう。
自分の経験から言えるのは
話し方は服装や物腰、見た目と同じレベルで
プレゼンの成功に影響がある
ということだ。
とても重要ではあるが、
コンテンツそのものではないので
決定的な要素ではない。
どんなに話し方が明快で素晴らしくても
中身の無い、得ることの無いプレゼンだったら
それは見た目だけきれいだが不味い料理と
何も変わらない。
話し方教室のようなところでは、
このプレゼンと話し方の関係が
しばしば整理されていない。
上手な話し方を否定したり
軽んじたりする気は一切ないが、
プレゼンの目的にとってそれは
最重要事項ではない。
プレゼンの目的は自分の思いを伝えて
相手に何らかの行動を促すことだから
コンテンツが7割である。
プレゼンをするということは、
「聞き手に何をプレゼントできるか」
「聞き手が求めているものは何か」
「聞いた人のために自分の持っている何が使えるか」
「なぜ自分は聞き手にこの提案をしているのか」
を伝える作業である。
そのために考え、十分な準備をし、
構成を決め、リハーサルをする。
だから本質的なことは
美しいスライドでも
明快でわかりやすい話し方でもない。
逆に言えば先の四項目がはまり、
きちんと準備されていれば
プレゼンとして70%はOKである。
ところでこの四項目、
「聞き手」というところを「お客」とか
「自分の会社」、「上司」に
置き換えてみてほしい。
そのまま自分が今為すべきことが
見えて来ると思わないだろうか。
Posted by グッドリスナー at
11:43
│Comments(0)
2014年12月19日
松下幸之助翁の口癖は「自分は平凡」だった
昭和の大経営者、松下幸之助翁の口癖は
「自分は平凡な人間」というものだった。
松下翁は、3人から始めた企業が
大パナソニックに至った要因として、
事業が時代に合っていたこと、
人材に恵まれたこと、
理想を掲げたこと、
企業を公のものと考えたこと、
ガラス張りの経営を行ったこと、
全員経営を心がけたこと、
社内の派閥をつくらなかったこと、
方針が明確であったこと
を挙げている。
だが、最も大きな要因は
「自分が平凡な人間だったこと」
であるという。
勿論たんなる大企業創業者というだけでなく、
現代の社会にも大きな影響を与えている
松下翁が平凡であるわけはない。
だが、本人は本当にそう思っていたようである。
平凡か非凡かは本人が決めることではなく、
他人の評価であるだろう。
松下翁の場合、「自分は平凡」という
信念から出発して、
人と組織の力を最大限に引き出していたことが
結果として非凡だったのだと思う。
自分を凡人と思うことで、
多くの人の考えを聞き、
知恵を借り、素直に考え、結論を出し、
決断し、実行し、継続するようになる。
自分は、人は誰もが非凡であると思っているが、
自分を凡人と位置づけることで非凡となる
こともまた出来るのだ。
2014年12月17日
TOEICで満点を目指すのは無意味であるということ
東洋経済オンラインで
東進ハイスクールの英語で有名な安河内先生と
TOEICの普及に長年尽力してきた
千田先生の対談が掲載されていて面白い。
千田先生は、早くからTOEICの創始者である
北岡先生(故人)とその普及に努めてきた。
だが、まだ試験を受ける側だったある時、
北岡先生に「次は満点を目指します」と言って
激しく叱責されたという。
北岡先生いわく、
「満点を目指すような人間をつくらない
ためにTOEICを作ったのだ!」
つまり、TOEICのテストは
結果が問題なのではなくて、
今のレベル、今からやることに必要な
レベルを正しく認識することが目的。
満点だから素晴らしいとか
600点だからダメというものではない
ということだ。
英語は満点を取ることが重要なのではなく
それぞれの目的に応じたレベルに
到達すればよいということなのである。
同時通訳者と旅行会話で求められる
レベルは同じではない。
英語に限らず、手段が目的化して
しまうことはたくさんある。
起業の世界でもいつしか勉強や
ノウハウを集めることが目的となり、
いつまでも追いかけ続ける人がいる。
どんな技能や経験もそれは手段であり、
それ自体が目的地にはなり得ない。
自省したい話である。
ちなみに千田先生の英語学習のモットーは、
The Key to success is
Starting and not stopping.
(成功の鍵は始めることと辞めないことだ)
そうである。
2014年12月17日
人手不足ならプロフィール強化は不要となるか?
急激な人手不足がやってこようとしている。
一部の業種では既に深刻な状況にあり、
人材確保が喫緊の課題になっているとも
言われている。
つい一二年前の就職氷河期、
人余り時代がウソのように
今は人の確保が難しいのだ。
労働市場は、
完全に労働者側の売り手市場になり、
就職や転職において、
もはや格別のキャリアアピールは
必要なくなったかのように見える。
このブログのテーマは、
埋もれているキャリアを発掘して錆びを落とし、
プロフィールとして強化し起業や就職に
役立てようというものだが、
もうその必要が無くなったと言えるのだろうか。
自分の考えは、
「むしろ売り手市場になったからこそ
自分にあった仕事に就くために
プロフィールを強化すべき」
というものである。
雇用市場が不況の時は、
自分に合っているかどうかは二の次で
とにかく「まずは就職」だったが、
今はなまじ選べるようになったので
適職につくための悩みが増したとも言える。
自分にフィットした、あるいは
自分がやるべき仕事は何なのか
今度は考えるようになる。
まして起業ということになれば
雇用市場の好不況に関係なく
自分の持つ強みをアピールしなくてはならない。
その意味で、ビジネスのプロフィール強化は
これから益々必要であり続けると確信している。
2014年12月16日
ナッツリターン事件 なぜ三代目は会社を潰すと言われるのか
財閥三代目のバカ娘が引き起こした
大韓航空のナッツリターン事件は、
子息への事業継承の難しさを象徴している。
日本のみならず韓国でも
「三代目が会社を潰す」とよく言われるそうだが、
それはなぜなのだろう。
自分は、
本人の積み上げたキャリアでない
親が作ってくれたキャリアと
本人の人格とのバランスが取れていないこと
に原因があると思う。
苦労は買ってでもしろとまでは言わないが、
くだんの財閥三代目副社長の場合、
米国の大学を出たのも、
大韓航空グループでのキャリアも
すべて本人の力で勝ち取ったものではなく、
父親であるグループ会長から
与えられたものである。
そこまでは、
創業者の親が後継者として自らの子息を
引き上げていく風景として
どこでもよくあることである。
問題は、成熟した人格というものは、
親が与えることの出来ないもので
本人しか獲得できないものであることだ。
人は様々な人と出会い、
喜びや悲しみ、苦しみを知り、
自分の力だけではどうにもならない
こともあることを知り、
少しずつ人格を成長させていく。
そうしたプロセスを経験できるのは
本人のみである。
大韓航空の副社長の場合、
現在の地位と人格のバランスが取れていない、
つまり「こども」だったということなのだろう。
しかしこのナッツリターン事件、
価値あるキャリアとは何かということを
示してくれているとも言える。
キャリア獲得の過程でやってきたことは、
結果が出たときもあれば出なかったこともある。
だが、そこで本人が全力を尽くしたこと
心血を注いでやったことというのは、
身についたキャリアとして成熟した人格を
形作ることに間違いなく寄与している。
三代目でも成功している経営者に
親とは無関係の会社で苦労してきた人が
多いのは偶然ではないのだ。
2014年12月15日
プレゼンの極意とは聞き手が心からしたいと促すこと
最近では「プレゼンテーション」
という言葉は誰でも知っていて、
何も特別なことではなくなってきている。
ビジネスの場だけでなく、
趣味やボランティアサークルでの発表や
団体での懇親の場など
非常に行う機会が増えてきている。
プレゼンのスキルに関する本も
たくさん出ているし、
セミナーやスクールも盛んである。
しかしプレゼンという行為の幅は
極めて広い。
人対人が接触する場で、
相手に何かの行動を促す行為には
すべてプレゼンの要素が含まれる
とも言われている。
自分自身、実務で数多くのプレゼンを聴き、
自分でもプレゼンをこなし、
さらにノウハウを人に教えるために
費用と時間をかけて学んできた。
その上で
「プレゼン上達のための極意とは」
と聞かれたらいったい何と答えるだろうか。
正解は無数にあるだろうが、
自分はプレゼンというのは、
「聴衆に何かの行動を促す」ことだから、
「行動を促すためのコツ」が極意だと思っている。
「脅迫や脅し」も行動を促すが、
あれはプレゼンではない。
プレゼンは、聞いた人が
「自分の意思で、心からそうしたい」
と思わせることを目的としている。
フーテンの寅さんのたたき売りの口上は
典型的なプレゼンだが、
あれは聞き手に何も強制していない。
お客が心から「ガマの油」買いたくなるのである。
ここにこそ、プレゼンの極意がある
と自分は思う。
聞く人に対して
「いかに心から(喜んで)〇〇したい」
と思わせられるか、
プレゼンはそれに尽きるといっていい。
例として商品プレゼンが分かりやすいが、
聞いた人に心から欲しい、
喜んで買いたいと思ってもらえれば
そのプレゼンは最善のものである。
つまりプレゼンの極意とは、
「聞き手の自然的に発生する行動の
手助けをすること」なのだ。
自分は「今買わないと損をする」とか
「知らないと大変なことになる」的な口上が大嫌いだが、
それは強迫(脅迫)のニオイがするからで、
プレゼンとしては最低であるからだ。
だから、聞く人が自分の感情で
そうしたいと思ってもらえるには
何をどのように説明したらいいか
ただそれだけを考える。
ハイセンスなスライドデザインや、
わかりやすい話し方も、
すべてはその目的を果たすために使われる
技術にすぎない。
2014年12月14日
囲碁上達の極意にスキル獲得の王道を見た
自分は囲碁をやらないが、
その上達の極意は二つしかないという。
一つは、「とにかくやってみる人」。
実際に碁をささずに批評だけの人、
学ぶばかりで実行しない人は上達しない。
二つ目は、「上達する勉強法を
確立している人」だそうである。
いま何をすべきか、
次に何をすべきか、
さらにその後何をどれくらいすべきか、
具体的なイメージを持っていない人は
無駄なことばかりやっていて上達しない。
進学塾で55段階指導というのがあったが、
まさに目的と行動の体系化、
自分なりのカリキュラム化は
やはり成功への王道のようである。
しかし、囲碁にかぎらず、
これは何かを身につけようとする時
何に対しても言えそうなことである。
高い目標でもステップを細分化し、
体系化して見えるようにし、
一つずつクリアしていく。
「実行」と「体系化」、
肝に銘じておきたい。
2014年12月13日
普通だと思っていることが人から見たらすごいスキルなのだ
先日ある会合の懇親会で知り合った人と
話していて、思わず膝をたたいて
賛同したことがある。
その人は超大手の電機メーカーを退職して
農業関係のビジネスを起業した人なのだが、
会社員がふだん会社でやっている
何気ない業務スキルが
違う場所、職場では大変重宝される
という話である。
例えば、業務報告資料や申請などの書類作成、
各種申告や手続きの業務、
報告書やプレゼン資料の作成等々。
ある程度以上の規模の会社では、
日常どこの職場でも普通に行われ、
特に高いスキルが必要であるとも思われていない。
だが、だが一歩会社員の世界から出ると
日常的にそのような業務をやっていないため、
そのような事務スキルが
すごいと高く評価される世界もあるのだ。
自分も以前、補助金申請の書類を作成し、
一回の申請で承認されたことがあるが、
書類作成を代行業者に依頼する人が多いと聞く。
だが、毎日のように業務報告や申請書類、
プレゼン資料を作っていた人間にとっては
そんな申請業務は「お茶の子の作業」であって、
それを高い報酬(20万円~70万円)で
人に委託する人がいるなんて
信じられないことだ。
あんなに簡単(自分の場合は3日くらいで作成)なのに
何で自分でやらないのだろうと思った。
しかし、日常的にそのような事務的な作業と
無縁な人や職場の人にとっては、
魔法のように思えることらしいのだ。
別に自慢話が目的なのではない。
どんな人でもその世界で
キャリアを積んできている人には
本人が気づかないだけで必要な人から
見たらすごいスキルが蓄積されている
ということなのだ。
それなのに、退職や転職などで
そんなすごいスキルを捨てて、
不慣れな新しいこと(資格取得など)を
身につけようとするのは実にもったいない。
付け焼刃でない本物のスキルは、
日々積み重ねてきた平凡な仕事の中にこそある。
そんな宝物を掘り出して、
誰かのために使ってあげなければ
浮かばれないではないか。
2014年12月12日
人のモチベーションを高めるマネジメント 秘訣は加点主義
昨日、とある会合でちょっと面白い
話を聞いた。
人のマネジメント、とりわけ評価というのは
加点主義の方が絶対にうまく行くという話だ。
人を評価し、育てたいという時
理想ラインから減点していくのではなく、
何もできないというライン(ゼロベース)から
出来たこと、評価出来ることを加点していく。
その方が結果として人は育つというのだ。
振り返って会社員時代を思い出してみると
評価はいつも目標に対する達成度合いで
測られていたことに気づく。
たぶんその方が、評価者が評価しやすい
という理由からなのだろうが、
評価される側としては目標をクリアする
ことだけのモチベーションしか湧いてこない。
さらにずる賢い人は、巧妙に
目標自体を高く設定されないようにする。
企業側としてはその弊害に対処するため
チャレンジ目標を設定させたりしているが、
これとて減点主義の物差しにしかなっていない。
減点主義の根源には学校教育があると思う。
学校の試験は、100点満点から
間違った設問ごとに減点されていく方式で
絶対に120点は取れない。
だが仕事なんていうものは、
100点が満点ということはなく、
やりようによっては120点や150点が
可能な世界である。
今自分は人を使う立場ではないが、
このことは肝に銘じておきたい。
話を聞いた。
人のマネジメント、とりわけ評価というのは
加点主義の方が絶対にうまく行くという話だ。
人を評価し、育てたいという時
理想ラインから減点していくのではなく、
何もできないというライン(ゼロベース)から
出来たこと、評価出来ることを加点していく。
その方が結果として人は育つというのだ。
振り返って会社員時代を思い出してみると
評価はいつも目標に対する達成度合いで
測られていたことに気づく。
たぶんその方が、評価者が評価しやすい
という理由からなのだろうが、
評価される側としては目標をクリアする
ことだけのモチベーションしか湧いてこない。
さらにずる賢い人は、巧妙に
目標自体を高く設定されないようにする。
企業側としてはその弊害に対処するため
チャレンジ目標を設定させたりしているが、
これとて減点主義の物差しにしかなっていない。
減点主義の根源には学校教育があると思う。
学校の試験は、100点満点から
間違った設問ごとに減点されていく方式で
絶対に120点は取れない。
だが仕事なんていうものは、
100点が満点ということはなく、
やりようによっては120点や150点が
可能な世界である。
今自分は人を使う立場ではないが、
このことは肝に銘じておきたい。