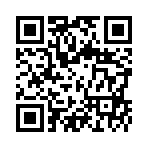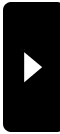2015年01月31日
メンタルの弱い人はどうすればいい?
心技体という言葉があるが、
仕事でもスポーツでも最後に決め手
となるのは「心」であることは間違いない。
ふだんは優秀な成績をおさめているのに
一発勝負の試験に弱い人、
オリンピックでは力が発揮できない選手は
メンタルが弱いといわれる。
しかしこのメンタル、
強い人もいれば弱い人もいる。
その違いが出る理由はおくとして、
メンタルが弱い、本番に弱い人としては
どうしたらこれを克服できるのだろうか。
自分とてメンタルが強いわけではなく、
打たれ強い人間でもないが、
人生経験から感じている克服法はある。
それは不安とか恐怖、心配というのは
相手、自分の外からもたらされるものではない
ということだ。
「〇〇になったらどうしよう」という心理は、
すべて自分の心の中のものであって、
相手から見れば自分が心配していようと
いまいと普通は何の関係も無いのである。
「普通は」というのは、
相手が故意に脅そうとかの意思が無い場合
という意味である。
恐喝者は、相手に恐怖感を意図的に植え付けて
メンタルを支配しようとする。
だが、そんな状況ではない普通の状況では、
ネガティブな感情はすべて自分の心が
生み出している産物だ。
だからメンタルを強化する方法は、
心の中の自分が生み出したネガティブ感情を
退治することである。
自分が「ここまでやったんだから」と
納得できるまでとことん準備するとか、
自分で自分に暗示をかけたり
思い切って気分転換するなど
方法は人によって様々である。
自分の場合、
どんなに仕事で大きなプレッシャーがかかる時でも
夜眠れないということが全く無かったが、
それは「心配しても心配しなくても
結果が同じなら、心配するだけ損だから
考えることそのものをやめよう」
と思っていたからだ。
自分がどう思っていようが
相手にとっては何の関係も無いのなら
自分が不安に思ったとしても
結果には何の良い影響ももたらさない。
まあ、一種の開き直りだが、
相手のあることはあれこれ心配しても
良い結果に対し全く無意味である。
2015年01月30日
プレゼンテーションにおいて伝え方や話し方より重要なこと
プレゼンテーションの話をもう少し続ける。
最近の若者は上手になってきているが、
日本人は欧米人に比べると
プレゼンテーションが下手だという。
その理由はいろいろあると思うが、
従来の日本的社会は、
何かの理解や合意を得る場面において、
論理よりも感情でのアプローチで
それを行ってきたという文化がある。
「以心伝心」「暗黙の了解」、
「場の空気で察する」文化においては
論理的な説明は重視されてこなかった。
しかしプレゼンテーションでは、
「結論はAである、なぜそう思うかその理由は
Bだからである」「その証拠はCである」、
「だからAという結論なのだ」
といった感じで相手に思いを伝えようとする。
これは「以心伝心」とは対極にある
作業である。
だから日本人がプレゼンテーションを
上手にやろうと思うのなら、
多少の努力が必要となるのはやむを得ない。
ではどんな努力が必要か、
伝え方や話し方は重要だが、
最も大切なことは、
自分自身が「伝えようと思っていることを
論理的に整理できていること」である。
自身の論理展開が破たんしているのに
いくら美しいスライドで流暢な話法で話しても
全くの失敗である。
だが、失敗プレゼンの多くは論理展開が甘く、
なぜそう言えるのかが論理的に
つながらないものが多い。
テクニックは重要だが、
本質そのものではない。
まずは自論を論理的に考察し、
論理を齟齬や破たんのないように
じっくりとまとめあげることが
大前提である。
2015年01月29日
成功するプレゼンの秘訣は至ってシンプルなのだ
仕事柄、プレゼンテーションを
聞く機会は非常に多い。
かつては圧倒的に話す側だったが、
最近は人の発表を聞く側の方が多い。
プレゼン内容は技術系の研究成果が多く、
かなり専門性の高い内容だ。
だが、発表者の方たちには申し訳ないが、
内容は良いのにプレゼンが下手過ぎだ。
世には山ほどプレゼンの書籍が溢れ、
学校でも職場でも接する機会が多いのに
これは何としたことだろう。
「プレゼンとは」という問いに対する答えは
意外とシンプルで、
要は「伝えたいことを伝えて
聞き手の行動を促すこと」に尽きる。
スピーチは話しっ放しでもよいが、
プレゼンは聞き手の何かを変えなくては
する意味が無い。
プレゼンをする理由は様々であっても
プレゼンで何かを伝えて
聞いた人が何かを感じ取って
次のアクションにつなげてもらう、
ただそれだけである。
たんなる報告的なプレゼンであっても
聞いた人の心に何かを残せれば
次の行動(心理や感情の変化も含む)
につながるのである。
理系の研究発表会などの場合は、
聴衆の属性が決まっているので、
的は絞りやすい。
短時間でランダムにいろいろな
分野の発表がされるようなプレゼンでは、
①なぜこの研究に着手したのか(聞き手との関係性)
②言いたいことを一言に要約すると何か(結論は何か)
③なぜその結論に至ると言えるのか(実証と立論理由、時に対論)
④これだけは伝えておきたいこと(結論の強調)
これに尽きる。
経験上も言えることだが、
プレゼンは短いほど難易度は上がり、
準備期間も長くなる。
TVコマーシャルは究極の短いプレゼンだが、
あの15秒や30秒という短い尺に伝えたいことを
込めるには並大抵でない努力と準備をしている。
さらに生の聴衆を相手にするプレゼンは、
舞台演劇のようなもので一発勝負。
自分はあがり症でという人は多いが、
練習、リハーサルで徹底的に磨きをかけずに
本番をうまく切り抜けようというのは
虫が良すぎる。
ただ、プレゼンは
流暢である必要は全く無い。
どんなプレゼンでも伝えたかったことが
伝わればそれは成功である。
成功への最も確実な道は、
聴衆がその日最も聞きたいことを
話すことである。
伝えたいことと聞きたいことが一致すれば
そのプレゼンは必ず成功する。
聞く機会は非常に多い。
かつては圧倒的に話す側だったが、
最近は人の発表を聞く側の方が多い。
プレゼン内容は技術系の研究成果が多く、
かなり専門性の高い内容だ。
だが、発表者の方たちには申し訳ないが、
内容は良いのにプレゼンが下手過ぎだ。
世には山ほどプレゼンの書籍が溢れ、
学校でも職場でも接する機会が多いのに
これは何としたことだろう。
「プレゼンとは」という問いに対する答えは
意外とシンプルで、
要は「伝えたいことを伝えて
聞き手の行動を促すこと」に尽きる。
スピーチは話しっ放しでもよいが、
プレゼンは聞き手の何かを変えなくては
する意味が無い。
プレゼンをする理由は様々であっても
プレゼンで何かを伝えて
聞いた人が何かを感じ取って
次のアクションにつなげてもらう、
ただそれだけである。
たんなる報告的なプレゼンであっても
聞いた人の心に何かを残せれば
次の行動(心理や感情の変化も含む)
につながるのである。
理系の研究発表会などの場合は、
聴衆の属性が決まっているので、
的は絞りやすい。
短時間でランダムにいろいろな
分野の発表がされるようなプレゼンでは、
①なぜこの研究に着手したのか(聞き手との関係性)
②言いたいことを一言に要約すると何か(結論は何か)
③なぜその結論に至ると言えるのか(実証と立論理由、時に対論)
④これだけは伝えておきたいこと(結論の強調)
これに尽きる。
経験上も言えることだが、
プレゼンは短いほど難易度は上がり、
準備期間も長くなる。
TVコマーシャルは究極の短いプレゼンだが、
あの15秒や30秒という短い尺に伝えたいことを
込めるには並大抵でない努力と準備をしている。
さらに生の聴衆を相手にするプレゼンは、
舞台演劇のようなもので一発勝負。
自分はあがり症でという人は多いが、
練習、リハーサルで徹底的に磨きをかけずに
本番をうまく切り抜けようというのは
虫が良すぎる。
ただ、プレゼンは
流暢である必要は全く無い。
どんなプレゼンでも伝えたかったことが
伝わればそれは成功である。
成功への最も確実な道は、
聴衆がその日最も聞きたいことを
話すことである。
伝えたいことと聞きたいことが一致すれば
そのプレゼンは必ず成功する。
2015年01月28日
日本の技術は次のステージに入った
最近我が家では
電気炊飯器を買い替えた。
どうせならということで奮発し、
当家にとってはかなり高額の製品を
購入した。
たかが炊飯器、そんな
に大きな違いはあるまいと思っていたが、
これが実に凄いのだ。
機能は数年前のものとそれほど
大きな違いは無いが、
炊き上がった米の見た目、
味は全く違う。
米のランクが確実に2ランクくらいは
上がったといって過言でない。
大げさでなく並みの市販米が、
魚沼産コシヒカリくらいになる。
これほどまでに炊飯器が凄くなっている
というのは自分だけの個人的感想ではなく、
中国人経済評論家の呉暁波氏も
同じことを言っている。
中国人が観光で日本に来ると
電気製品を買い求めることはよく知られているが、
最近の売れ筋は電気炊飯器と洗浄便座である。
経済評論家の呉暁波氏が、
炊飯器では中国トップの家電メーカー技術者に
「日本製炊飯器は本当に神秘的なほど
すごいのですか?」と尋ねたところ
技術者はしばしの沈黙の後、うなずき、
「我々としては、どうすればよいのか
わかりません」と答えたという。
炊飯器は精密な電子制御と釜が命だが、
釜のように単純に見えるものに
最近は凄い技術が集積されていて、
とても真似できないものなのだそうだ。
電気炊飯器や洗浄便座は、
世間一般にはハイテクではなく、
むしろローテクと思われているだろうが、
最近はローテクの分野に
様々なハイテクが込められるようになり、
日本の技術はあきらかに新しいステージに
入ったと感じられる。
日本はこのようなローテクとなった分野での
ハイテク注入ノウハウが素晴らしく、
衣食足りて量から質に転換が進んでいく
これからの世界をリードしていくことは
間違いないと確信している。
2015年01月27日
自分の居場所とは、誰かの役に立っていると実感できる場所
自分の友人は年齢層が幅広く、
下は20代から、上は80代の人までいる。
先日、その中の今年85歳になるMさんと
会合で一緒になり、
いろいろな話を聞く機会があった。
Mさんいわく、
日本の高齢者福祉は決定的な
勘違いをしているという。
ひと口に老人といっても
健康状態も精神状態も実に様々で、
今の高齢者にとって押し付けになっている
施策も多いという。
特に勘違いが甚だしいのは
「高齢者の生きがい」についてで、
どんなことに生きがいを感じるかが
まるで理解されていないという。
Mさんに言わせれば、
高齢者が最も生きがいを感じるのは
「人から頼りにされている時、
人の役に立っていると実感できるとき」
だそうである。
よく地方で、90歳を過ぎてなお現役で
農業などに従事している高齢者の人がいるが、
あれは生活や目先のカネ勘定ではなく、
自分が誰かに貢献している、
喜ばれているということを通じて
社会の一員であることが
確認できるということが大きいのだろう。
そんなわけだから、
Mさんは旅行や観劇をしたりすることよりも、
趣味の陶芸で作品を造ることよりも、
造ったものがわずかな金額でも売れ、
買った人に喜んでもらえた時
最も生きがいを感じるという。
核家族化が極限に達している現代では
想像しにくいが、
かつての大家族社会では老人といえども
必ず何かの役割りがあって、
家族やコミュニティに貢献していた。
だからつねに居場所があり、
生きがいが論じられることも無かったのだ。
かつてある人から
「人の役に立つ仕事をしたい」と言ったら
「それも自分目線の一種のエゴ」と言われた。
だが、世の中の誰にも貢献しない仕事に
生きがいなんか感じるはずがない。
かつて聞いた話だが、
囚人にとって最も辛い課役は、
「地面に穴を掘らせ、それを埋めることを
毎日延々と続けさせることである」という。
人は行動に意味があるからこそ
継続できるのであり、
誰かに貢献していると思えるから
生きていると実感できるのだ。
先年叔母が亡くなったが、
彼女はその少し前まで老いた妹を
自宅で老老介護していた。
本人にとっては大変な負担だったろうが、
妹にとっては必要な人であることに
生きがいがあったのかもしれない。
叔母は妹が亡くなって
ほどなく自分も旅立ったのだから。
2015年01月26日
プロとは何か ビートたけしが若手芸人を叱った言葉
アサ芸プラスに面白い記事があった。
記事は、たけしとたけし軍団が
勢ぞろいした生放送で
オンエアしていない時に起きた
出来事についてのものである。
番組ではたけしがMCを務め、
好き勝手な進行とデタラメな発言を繰り返し、
それに対し軍団全員が客席から
容赦なく野次を飛ばしてツッコむという内容。
放送開始直後、ある若手芸人の飛ばした野次が、
たけしの中でどうにも許せなかったようで、
CMに入った途端、顔色を変えたたけしは、
「おい、お前の野次は何だよ!
つまんねーことばっかり言いやがって!」
とマジ切れしたという。
その場にいた記事を書いた人によると、
若手芸人の野次は確かにたけしが怒るのも無理はない、
お門違いな野次だったそうだ。
オンエアに戻るとたけしは
何事もなかったように“明るいたけちゃん”に戻り、
その後、番組は盛り上がり、無事に生放送を終了した。
その後、忘年会も兼ねた真夜中の打ち上げがあり、
お開きの時、たけしが語った言葉は、
「今日はちょっと収録中に怒ったけど、
俺たちはプロなんだから、それで飯を食ってんだから。
他がダメでも何でもいいんだけど、
お笑いだけは誰よりも気を配って、
神経を使ってやらなきゃダメなんだ」
というもの。
たけしは、
流れにまかせて無神経な(プロとしての自覚の無い)
野次を飛ばした、その軽率さに対して
無性に腹が立ったのだ。
これはたんに「すべる=受けない」
というのとは違うだろう。
若手芸人の野次の内容はわからないが、
おそらくプロのお笑い芸人らしくない
発言だったのだろう。
この話、プロとしての仕事に対する
心構えを考えさせてくれる。
およそプロとして周囲に期待されることは、
その道の専門家としての才智である。
レベルの高い低いはともかく、
日常の多くの時間をそれに割き、
専心しているからこそ得られる何かを
人は期待しているのだ。
どんな職業であれ、ビジネスであれ、
その道のプロと呼ばれることが
どんなことを期待されてのものか
よくよく考えなくてはならない。
2015年01月25日
「この人と不幸になってもいいと思う人と結婚しなさい」
「この人と不幸になってもいい
と思う人と結婚しなさい」とは、
部屋の日めくりカレンダーにあった言葉である。
別に著名な人の言葉ではないが、
相手目線のいい言葉だと思う。
毎年離婚件数は増加しているが、
もしも皆がこの言葉のような結婚をしていたら
離婚件数は減少するのかもしれない。
先ごろおしどり夫婦と呼ばれていた
タレント夫婦が離婚裁判中であると報じられたが、
自分は結婚とは相手への感謝を持続する
ことだと思っている。
夫婦は知り合うまでは赤の他人、
それが長く一緒でいられるためには
相手へのリスペクトが欠かせない。
だが結婚当初の緊張感は次第に薄れ、
日頃ついつい尊敬や感謝の気持ちを忘れてしまう。
外で働くこと、家事をこなすこと
こどもを育てること
家系を切り盛りすること
どんな些細なことにも感謝を感じ、
相手を尊敬する。
そしてそれを言葉に出したり、
行動で表すことである。
ところで今日のこの言葉、
他のことで言い換えも出来そうだ。
「この会社でなら苦労してもいい
と思う会社に就職しなさい」
はどうだろうか。
2015年01月24日
40歳を過ぎたら、自分の後半生のライフプランを真剣に考えよう
定年延長や再雇用で65歳まで
会社勤めをする人が多くなった。
それを選択するかしないかは
もちろん個人の考え方次第である。
だが、40歳を過ぎたら、どんな人も
自分の後半生のライフプランは
真剣に考えた方がいい。
いうまでもなく、人生は有限であり、
健康年齢(健康で活動できる年齢)は
より限られている。
ふだん、人にとって「死」は概念でしかなく、
現実性を持っていない。
しかし戦争や大災害を体験したり
身近な人が亡くなったりすると
人生が有限、それもそんなに多くの時間が無い
ことに気づくことになる。
自分の場合は、両親が相次いで
亡くなった時にそれを強く感じた。
神戸や東北の震災では、
震災後に人生観がガラっと変わった人が
多くいるという。
「自分はなぜこの世に生を受けたのか」、
「何をするために生まれてきたのか」、
ミッションを考えずにはいられなくなる。
もしライフプランを考えなければ、
惰性で働き、完全退職後は目標を
見失った毎日に遭遇する可能性が高くなる。
それはとても不幸なことだ。
自分のミッションが仕事とはかぎらない。
家族を大切にする、
趣味をきわめる
若い頃に出来なかったことをやり尽すなど
いろいろあるだろう。
だが、結局人とはそれを知るために
死ぬまで生きているということに気づかされる。
40歳くらいが人生の時間的
折り返し地点だとすると、
ちょうど分水嶺の上に立っているわけで、
全体を見渡せるはずだ。
もっとそれより早くライフプランを
イメージできているのなら
それはそれで素晴らしいが、
山の前半では不確定要素が多すぎ、
たぶん予定通りにはなかなかいかないだろう。
いずれにしても一回限りの人生、
自分の青い鳥はイメージできるように
したいものである。
2015年01月23日
正社員という働き方しか選択できないことこそ問題
日本の労働人口は人口減社会に
突入したこともあって
今後減少の一途をたどるものと予想されている。
2013年に6577万人だった労働人口は、
2030年には5683万人、
2060年には4390万人にまで減少する。
(内閣府の試算による)
マクロかつロングスパンで見れば
最近の人手不足は一時的なものではなく
今後恒常化する状況にある。
わずか50年弱で4割近くも働き手が
減る社会というのは想像すらできないが、
あらゆる社会分野に大変な影響がある
ことは必至である。
そこで叫ばれているのが
外国人労働者や移民資格の緩和、
育児女性の就業促進と高齢者の活用である。
前者の外国人大量受け入れは、
民族問題や宗教問題という大きな火種を
かかえることが欧米の事例からも強く懸念されている。
では後者の育児女性の就業促進と
高齢者の活用についてはどうだろうか?
たしかに育児女性の就業率を85%にまで引き上げ、
働ける高齢者の雇用を促進すると労働人口は、
2030年には何もしない場合の5683万人から6285万人に、
30歳から49歳の育児女性の就業率を
北欧並みの90%にまで高めれば
2060年には何もしない場合の4390万人から
5407万人にとどめることが出来るという
シュミレーション予測もある。
だが、現実には大きなハードルがある。
ハードルはいくつかあるが、
最も大きなハードルは硬直的な雇用形態と
ジョブディスクリプション概念の不徹底だと
自分は思っている。
育児中の専業主婦の女性は、
かつて企業の第一線でバリバリ働いていたように
正社員として働きたいかというとそうではない。
小さい子を預けるリスクと経済的肉体的負担、
職場にかける迷惑を思うと正社員として
就業することには大きなためらいがあるのだ。
働きたい、社会とつながっていたい、
社会に必要とされる存在でいたい
という思いはあっても
正社員という雇用形態しか選択できない
ことが大きな足かせになっている。
雇う側も、ジョブディスクリプションが中途半端で、
本来はそれが十分に可能であるにも関わらず
実行できていない。
経験からも言えることだが、
もはや現代の企業業務で正社員でなければ
出来ないことなどほとんど無いといってもいい。
(経営者すらも)
企業はもっとジョブディスクリプションを明確にし、
正社員という雇用形態にこだわらずに
業務を分割発注すればいいのである。
現実にフルタイムではなく、
ある業務だけを請け負うとか
あるプロジェクトだけ手伝うといった
働き方を求め成功している企業が現れ始めている。
また個人起業家の知人は、
自身のウェブサイトやブログ、メールの管理、
請求入金のオペレーション業務を業務別に
ネット上で子育て中の主婦にすべて業務委託している。
さらに育児期間というのは、
主婦にとってもたんなる就業ブランク期間ではなく、
実は企業側にとっても大きな価値を持っている。
親になればわかることだが、
子育てを経験しないと決してわからないことも
世の中にはたくさんあるのである。
就業人口が減って大変だと
いたずらにうろたえるのではなく、
働き方に多様性を持たせる考え方が
今こそ必要とされていると考えるべきなのだ。
2015年01月22日
なぜ日本では貴重な人材が還流しにくいのか?
ちまたで中高年のセカンドキャリアが
最近よく取り上げられる。
だが、大企業の高いスキルを持った人材が、
それを切望している中小企業に
うまく還流していないのはなぜだろうか。
一つには再雇用制度が法律で義務化
されたことも理由だろう。
年金支給年齢に達するまで
定年後も勤めていた会社に残れるので
あえて小さな会社で苦労しなくても
と考える人は多い。
しかしそれ以上に
「自分のスキルなど今までの会社だから
通用するもので、
会社を離れたら何もできない」
と思っている人が多いように見える。
日本の会社の帰属意識養成技術は
たいしたもので、
社員に対し実際にはいろいろ出来るのに
会社があってこそと巧妙に思い込ませている。
以前にも書いたが、
子象と杭の関係である。
象は子象の時、子象の力では
抜けない杭につないでおくと
大人になってそんな杭など簡単に
引き抜ける力をつけても
杭とはぬけないものと
思い込まされているので
決して杭を引き抜いて逃げない
のだそうだ。
自分が知るかぎり、
特に大手の企業で管理職だった
ような経歴の持ち主は
非常に高いスキルや仕事のリテラシー
を持っている。
そんなスキルなど会社の中だけで、
たいした価値は無いと思うのは勝手だが、
そんな人は長年にわたって杭は
抜けないと思い込まされてきた
象を彷彿とさせてくれるのである。
会社側にとっても、
報酬が三分の一になって
モチベーションの下がった人を
雇い続けるデメリットがある。
本人のためにも会社のためにも
新天地への人材の還流を
真剣に考えるべきときである。